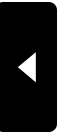山の挽歌-松田白作品集-
2009年01月21日
Sの家
樹陰に陽のこぼれる石畳の坂道を、トンカントンカンとのんびり木霊する船大工の槌の音を背に、私達は登っていった。ほかには何の音もしない。狭い石畳の道は、どこまでも続く。雨の多い島なのである。緑の奥に屋根だけをちらほらさせる民家が、わずかに人の生活を匂わせていた。だった一人行き会った老婆は、立ち止まって丁寧に頭を下げた。両側に続く生垣の道を二十分ほども歩いただろうか、道は海に向かって下る。左側の山茶花(さざんか)の垣根が途切れると、黒く塗られた立派な門が現れた。そこがSの家だった。
玄関に導く青い敷石の両側には、今が盛りのトベラの白い花が咲き乱れ、その特異な匂いを漂わせていた。Sに続いて玄関に入ると、いきなり正面の立屏風の虎が目に飛び込んだ。真赤な口をクワッと開いて、金色の眼が私をにらんでいる。不用意に飛び込んでしまった武家屋敷、私にはそんな第一印象があった。
「ただいま、私よ」
Sの声に出てきたのは、和服の似合う上品な婦人だった。
「男の子、拾ってきちゃった。泊めてやって……」
Sの陰に小さくなっていた私に、婦人は頬を綻ばせた。
「まあまあよく。このハネッ返りの母でございます。さあ遠慮しないで、どうぞ」
こうして通された青畳の匂う十畳に、私は一人ぽつんと取り残された。Sはなかなか出てこない。紫檀の卓子の上には漆塗りの菓子皿に厚切りの羊羹がひと切れと、真白に粉をふいた干し柿が、ふっくらと置かれていた。Sの母の人柄とこの家の品格のようなものに気押しされて、私は茶菓に手が出ない。
お茶だけ飲むと、いっぱしの芸術品に見える羊羹の黒ずんだ紫を見つめているだけだった。
二十分もそうしていただろうか。静かに襖(ふすま)が開いて、黄八丈に濃紫の帯を締めた娘さんが手をつかえた。私はびっくりして座布団から跳びすさったが、ゆっくり顔を上げた娘さんはまさしくSだった。
「エヘヘ」と笑うと、Sは言った。
「どうだ、驚いたか! 見違えるほど女らしいだろう」
強要されては、お世辞にも女らしいとは言えなかった。
「うん、驚いたよ。やはり姉さんも女か? 化け方がうまいや」と、やっと切り返した。
しかし白粉気こそなかったが、紫の三尺が似合う娘らしい娘だったのである。Sはずかずかと私の隣にきて足を崩すと、「何さ、まだ食べてないの。お腹空いているんだろう」と言った。
「だって、この芸術品みたいなの、なんとなく手が出ないよ」
「馬鹿ね。それ、私が買ってきた虎屋の羊羹だよ。干し柿は母の手製。食べなさいよ。後でお腹の膨らむもの作ってやるからさ」
「あーあ、やんなっちゃうなあ。姉さんは雰囲気も何もぶっ壊しだよ」
「言うわね。何さ、借り物の猫みたいに……。そんな柄じゃないだろう」
「えーえ、どうせ捨て猫ですよ」
私は羊羹を頬張った。何を隠そう、ぺこぺこにお腹が空いていたのである。
空け放された庭の木立越しに海が見えていた。母屋の左手は鉤の手に曲がって、レンガ造りの洋館である。白いレースのカーテンが風にそよいでいる。広い庭だった。芝生に花壇が切ってあり、洋館に沿って浜木綿(はまゆう)が白い花を咲かせていた。
「いいなあ……。こんな所に僕も住みたいよ」
「いいもんか、こんな家、非能率的で……。でも花は奇麗でしょ。母はこのお花を切って、毎日のように父のお墓に供えるのよ。島の習慣だけどね。お墓の花は絶やさないの。後でお墓に行ってみようよ」
その夜、私は生前の父上が使用していたという洋館のベッドに寝かされた。マントルピースの上の古いモデルシップが落ち着いた雰囲気を漂わせ、久しぶりの深い眠りに私を誘ったのである。
玄関に導く青い敷石の両側には、今が盛りのトベラの白い花が咲き乱れ、その特異な匂いを漂わせていた。Sに続いて玄関に入ると、いきなり正面の立屏風の虎が目に飛び込んだ。真赤な口をクワッと開いて、金色の眼が私をにらんでいる。不用意に飛び込んでしまった武家屋敷、私にはそんな第一印象があった。
「ただいま、私よ」
Sの声に出てきたのは、和服の似合う上品な婦人だった。
「男の子、拾ってきちゃった。泊めてやって……」
Sの陰に小さくなっていた私に、婦人は頬を綻ばせた。
「まあまあよく。このハネッ返りの母でございます。さあ遠慮しないで、どうぞ」
こうして通された青畳の匂う十畳に、私は一人ぽつんと取り残された。Sはなかなか出てこない。紫檀の卓子の上には漆塗りの菓子皿に厚切りの羊羹がひと切れと、真白に粉をふいた干し柿が、ふっくらと置かれていた。Sの母の人柄とこの家の品格のようなものに気押しされて、私は茶菓に手が出ない。
お茶だけ飲むと、いっぱしの芸術品に見える羊羹の黒ずんだ紫を見つめているだけだった。
二十分もそうしていただろうか。静かに襖(ふすま)が開いて、黄八丈に濃紫の帯を締めた娘さんが手をつかえた。私はびっくりして座布団から跳びすさったが、ゆっくり顔を上げた娘さんはまさしくSだった。
「エヘヘ」と笑うと、Sは言った。
「どうだ、驚いたか! 見違えるほど女らしいだろう」
強要されては、お世辞にも女らしいとは言えなかった。
「うん、驚いたよ。やはり姉さんも女か? 化け方がうまいや」と、やっと切り返した。
しかし白粉気こそなかったが、紫の三尺が似合う娘らしい娘だったのである。Sはずかずかと私の隣にきて足を崩すと、「何さ、まだ食べてないの。お腹空いているんだろう」と言った。
「だって、この芸術品みたいなの、なんとなく手が出ないよ」
「馬鹿ね。それ、私が買ってきた虎屋の羊羹だよ。干し柿は母の手製。食べなさいよ。後でお腹の膨らむもの作ってやるからさ」
「あーあ、やんなっちゃうなあ。姉さんは雰囲気も何もぶっ壊しだよ」
「言うわね。何さ、借り物の猫みたいに……。そんな柄じゃないだろう」
「えーえ、どうせ捨て猫ですよ」
私は羊羹を頬張った。何を隠そう、ぺこぺこにお腹が空いていたのである。
空け放された庭の木立越しに海が見えていた。母屋の左手は鉤の手に曲がって、レンガ造りの洋館である。白いレースのカーテンが風にそよいでいる。広い庭だった。芝生に花壇が切ってあり、洋館に沿って浜木綿(はまゆう)が白い花を咲かせていた。
「いいなあ……。こんな所に僕も住みたいよ」
「いいもんか、こんな家、非能率的で……。でも花は奇麗でしょ。母はこのお花を切って、毎日のように父のお墓に供えるのよ。島の習慣だけどね。お墓の花は絶やさないの。後でお墓に行ってみようよ」
その夜、私は生前の父上が使用していたという洋館のベッドに寝かされた。マントルピースの上の古いモデルシップが落ち着いた雰囲気を漂わせ、久しぶりの深い眠りに私を誘ったのである。
2009年01月22日
地獄(1)
傾いた陽に黒い影を落として、石畳の道を先に立って登っていくのはSである。黒地に白の大柄な飛白(かすり)を着て、蜂のようにくびれた胴に赤い三尺を無造作に締めている。「帯なんか、苦しくって」という彼女なのだが、おかっぱの少女が締める三尺が、ちっとも不自然には見えなかった。むしろ奇妙ななまめかしさが私には感じられた。それはSの外人並みの腰の線や、そのあたりまで垂れ下がった長い髪のせいだったかもしれない。私はふと、彼女には異国人の血が流れているのではないか?とさえ思った。彼女の肘から曲げられた腕には籐で編んだ大きな篭が提げられていたが、何が入っているのか私は聞きもしなかった。
私は半袖のシャツに紺のズボンという平凡な服装だったが、手には不相応に大きなランタンをぶら提げていた。それは船乗りが使う時代物の大型ランタンだった。どんな嵐の中でも大丈夫という代物だけあって、ホヤのガラスは太い針金の編目で保護されていて、はなはだしく重かった。
「今日は夕焼けを見て帰りが暗くなるから、懐中電灯を持っていこう」と言うSに、私はランタンを持っていこうと提案したのだ。土間の梁に下げられて埃だらけになっていたのを、私が奇麗に掃除したものだ。
「そんなもので気分出そうっての? ロマンチストさん!」と冷やかされたが、「好きだねえ、重いのにご苦労さん」と、反対はしなかった。私は橙色のその柔らかい明かりが好きだ。大きなこのランタンは、広い範囲を柔らく照らすに違いなかった。
集落を抜けると、椿の荘園の中を行く。すでに花は落ち、濃緑の葉の間に薄い緑の実を覗かせていた。下枝を伐り払われた灰色の滑らかな木肌が、整然と立ち並んでいる。葉陰で首を傾ける四十雀(しじゅうから)が可愛かった。
道はやがて雑木林に入り、紫陽花(あじさい)の花が目立つようになる。淡青の手毬(てまり)花が陽の傾いた林の中に幾つも浮かびあがった。その中にひときわ白く咲き匂うのは、トベラの花である。それはところどころ細くなった道をふさぎ、花に触れまいと重いランタンを持ち替える手が忙しい。でもその細かい花びらは、道に散り敷いていた。トベラの花の匂いは悪臭と感じる人がいるかもしれない。しかし、仄(ほの)かに匂う時のそれが私は好きだ。
島ではこの木をシッチリバッチリの木と呼ぶ。この木を燃やすときの音からきたものだという。お正月にトベラの枝を燃やして悪魔払いをするというのも、燃える時の臭いで悪魔を追い払うのだろう。私は島の人々の生活がにじみ出たその名に、一層の親しみを感じた。
松の梢を渡る風の音だったろうか、海蝕崖を洗う波の音だったろうか、遠くに絶え間ないざわめきがあった。ランタンは重かったが、Sと歩くこの道が、私にはこの上もなく楽しかった。Sはしかし、私の気持ちも知らぬげに足を速めた。
間もなく道は海蝕崖の上に出て、途絶えたように思われた。Sは道を離れ、潅木を押し分けて小高い丘を目指して登っていく。そこは海蝕崖の突端で、背の低いトベラやツツジの点在する小さな草原になっていた。眼下に太平洋、そして背後には黒松の林が続いていた。Sは崖の縁に立つと、目の下の海際や海中の岩礁に牙のように突っ立つ幾つかの岩塔を指差して言った。
「あれがG岩、こっちがN岩、向こうがM湾よ。もうじき陽が沈むわ……。ここの夕焼け素晴らしいの。私、大好き」
M湾は海蝕崖に囲まれた円い弧を描いた大きな湾で、昔の噴火口の跡だという。大小の岩礁や岩塔が顔を出し、海の青一色は、そこだけが波に噛まれて白く泡だっていた。
私達はSの手製のデセールをボリボリかじりながら夕映えを待った。
夕照(せきしょう)は美しく、そして儚(はかな)いものだ。その儚さゆえに美しいのかもしれない。空にピンクが刷かれると水平性が金色に輝き、波がラメの布地を織ると見る間に大気は真紅に染まる。海風に乱れる髪を掻き上げるSの指を、腕を赤々と照らして、一刻(ひととき)の休みもなく紫から青黒に沈潜していく。
私達は声もなく息をつめ、その短い時刻(とき)を追う。惜しむ暇もない、その時刻を追う。そしていつか、黄昏が風景に忍び寄る。
私は半袖のシャツに紺のズボンという平凡な服装だったが、手には不相応に大きなランタンをぶら提げていた。それは船乗りが使う時代物の大型ランタンだった。どんな嵐の中でも大丈夫という代物だけあって、ホヤのガラスは太い針金の編目で保護されていて、はなはだしく重かった。
「今日は夕焼けを見て帰りが暗くなるから、懐中電灯を持っていこう」と言うSに、私はランタンを持っていこうと提案したのだ。土間の梁に下げられて埃だらけになっていたのを、私が奇麗に掃除したものだ。
「そんなもので気分出そうっての? ロマンチストさん!」と冷やかされたが、「好きだねえ、重いのにご苦労さん」と、反対はしなかった。私は橙色のその柔らかい明かりが好きだ。大きなこのランタンは、広い範囲を柔らく照らすに違いなかった。
集落を抜けると、椿の荘園の中を行く。すでに花は落ち、濃緑の葉の間に薄い緑の実を覗かせていた。下枝を伐り払われた灰色の滑らかな木肌が、整然と立ち並んでいる。葉陰で首を傾ける四十雀(しじゅうから)が可愛かった。
道はやがて雑木林に入り、紫陽花(あじさい)の花が目立つようになる。淡青の手毬(てまり)花が陽の傾いた林の中に幾つも浮かびあがった。その中にひときわ白く咲き匂うのは、トベラの花である。それはところどころ細くなった道をふさぎ、花に触れまいと重いランタンを持ち替える手が忙しい。でもその細かい花びらは、道に散り敷いていた。トベラの花の匂いは悪臭と感じる人がいるかもしれない。しかし、仄(ほの)かに匂う時のそれが私は好きだ。
島ではこの木をシッチリバッチリの木と呼ぶ。この木を燃やすときの音からきたものだという。お正月にトベラの枝を燃やして悪魔払いをするというのも、燃える時の臭いで悪魔を追い払うのだろう。私は島の人々の生活がにじみ出たその名に、一層の親しみを感じた。
松の梢を渡る風の音だったろうか、海蝕崖を洗う波の音だったろうか、遠くに絶え間ないざわめきがあった。ランタンは重かったが、Sと歩くこの道が、私にはこの上もなく楽しかった。Sはしかし、私の気持ちも知らぬげに足を速めた。
間もなく道は海蝕崖の上に出て、途絶えたように思われた。Sは道を離れ、潅木を押し分けて小高い丘を目指して登っていく。そこは海蝕崖の突端で、背の低いトベラやツツジの点在する小さな草原になっていた。眼下に太平洋、そして背後には黒松の林が続いていた。Sは崖の縁に立つと、目の下の海際や海中の岩礁に牙のように突っ立つ幾つかの岩塔を指差して言った。
「あれがG岩、こっちがN岩、向こうがM湾よ。もうじき陽が沈むわ……。ここの夕焼け素晴らしいの。私、大好き」
M湾は海蝕崖に囲まれた円い弧を描いた大きな湾で、昔の噴火口の跡だという。大小の岩礁や岩塔が顔を出し、海の青一色は、そこだけが波に噛まれて白く泡だっていた。
私達はSの手製のデセールをボリボリかじりながら夕映えを待った。
夕照(せきしょう)は美しく、そして儚(はかな)いものだ。その儚さゆえに美しいのかもしれない。空にピンクが刷かれると水平性が金色に輝き、波がラメの布地を織ると見る間に大気は真紅に染まる。海風に乱れる髪を掻き上げるSの指を、腕を赤々と照らして、一刻(ひととき)の休みもなく紫から青黒に沈潜していく。
私達は声もなく息をつめ、その短い時刻(とき)を追う。惜しむ暇もない、その時刻を追う。そしていつか、黄昏が風景に忍び寄る。
2009年01月23日
地獄(2)
Sが突然立って言った。
「さあ、行こう」
私はびっくりしてSを見た。
「もう帰るの?」
「これから、まだ行く所があるの……。行こうっ」
Sは私の手を引っ張って立たせた。
歩きながら、Sはトベラの花房を摘んでは篭に入れている。私もSと肩を並べた。この夕暮れに、Sはどこへ私を連れていくというのだろうか。
「どこへ行くのさ?」と私は聞いた。
黄昏の中でSは立ち止まり、私の眼を覗き込んで笑った。
「地獄へ行くんだよ」と、小さな声で言う。
「えっ、地獄?」
「そう、地獄さ」
Sの低い声に冗談と知りつつ、私は何か知れずぞっとするものを感じた。
元の道に戻ると、Sは断崖の方に歩み寄る。
「飛び降りるのでは? まさか」
一瞬そんな予感めいたものを感じた私は、すぐそのばかばかしさに苦笑した。崖淵で振り返ったSが微笑して言う。
「ここから降りるよ。道があるのさ」
道は途絶えていると思ったのだが、実はそうではなかった。急な崖の岩壁には、電光形にかなりしっかりした足場が刻まれてあった。
「滑って落ちた慌て者もいるのだから、気をつけなさいよ」と再び言い、Sはどんどん下っていく。
道の悪さより、私には右手六十メートルはあろう垂直の岩壁の真下の薄闇がひどく気味悪かった。そのあたりには黒い海が入り込んでいて、白く泡だった海水が、何か得体の知れない獣が蠢(うごめ)き息づいているように見えたからだった。
降路の正面には崖下からそそり立つ二つの岩塔が黒々と立ちはだかっていたが、ちょうどそれは高さ四十メートルを越える大岩塊を、巨大な鉈で一気に割り裂いたもののように見えた。
「あれが地獄?」と聞くと、低い声で「違うよ、あれは地獄の門」とSは答える。
下りきった地獄の門のあたりは薄闇に包まれていた。湿った空気の漂いの中で、Sの顔が微笑んだ。
「あの門をくぐって、二人で地獄に落ちようよ」
私の背すじを、またしても冷たいものが走った。別に怯えていたわけでもないのに、「おどかさないでよ」と言う私の声は少し嗄(か)れていた。
地獄の門の岩壁の狭間には細い道が吸い込まれていたが、その限られた狭い空間の向こうには明るく白い海が光っていた。
そこは岩塊がごろごろと積み重なっている岩礁で、足元の岩盤の溝には赤茶けた水がたまっていた。磯の香に混じって、異様な臭いが鼻をかすかに刺激した。
「三途の川よ」と言って、Sは溝を飛び越えた。
大岩をぐるりと回ると、その岩陰にかなり大きなタイドプール(引き潮の時、海岸の岩間に海水が取り残されてできる水溜り)があった。しかしそれはただのタイドプールではなくて、水面に白い湯気を漂わせている海辺に湧く温泉だった。「そういえば、この島は火山島だったっけ」と、今さらのように私は温泉の存在を認識するのだった。
「なーんだ、温泉か!」
「そうさ、坊やを洗ってやろうと思ってね」
天然の岩風呂は三方を大岩に囲まれ、海側だけが開いていて、そこから岩の裂け目を通じてすぐ前の海と連絡していた。波が寄せるたびに海水は湯船の中に少しずつ入り込んでいた。大潮の時はたぶん海面下になるのだろう。付近の岩床や岩塊には薄緑の藻類が付着していた。湯船は広く、いくらか濁っていて底は見えなかった。奥は岩の陰で暗かった。前面の海には幾つもの岩礁が入江を鎧(よろ)うように立ち並び、それらはみな水蝕によって奇怪な形に削られていた。空にも海にもまだ残光があったが、背後を限る島の岩壁は上部のピンクを残してすでに夜の色だった。
私は平らな岩の上に腰を下ろして、傍らにランタンを置いてから言った。
「姉さんに、すっかりおどかされちゃった」
Sも私の横に腰を下ろし、笑って「地獄のことか……」
そして後を言わずに、じっと空を見上げていた。
「地獄か……」
再びSは独り言のように言ったまま、黙り込んでしまった。
「さあ、行こう」
私はびっくりしてSを見た。
「もう帰るの?」
「これから、まだ行く所があるの……。行こうっ」
Sは私の手を引っ張って立たせた。
歩きながら、Sはトベラの花房を摘んでは篭に入れている。私もSと肩を並べた。この夕暮れに、Sはどこへ私を連れていくというのだろうか。
「どこへ行くのさ?」と私は聞いた。
黄昏の中でSは立ち止まり、私の眼を覗き込んで笑った。
「地獄へ行くんだよ」と、小さな声で言う。
「えっ、地獄?」
「そう、地獄さ」
Sの低い声に冗談と知りつつ、私は何か知れずぞっとするものを感じた。
元の道に戻ると、Sは断崖の方に歩み寄る。
「飛び降りるのでは? まさか」
一瞬そんな予感めいたものを感じた私は、すぐそのばかばかしさに苦笑した。崖淵で振り返ったSが微笑して言う。
「ここから降りるよ。道があるのさ」
道は途絶えていると思ったのだが、実はそうではなかった。急な崖の岩壁には、電光形にかなりしっかりした足場が刻まれてあった。
「滑って落ちた慌て者もいるのだから、気をつけなさいよ」と再び言い、Sはどんどん下っていく。
道の悪さより、私には右手六十メートルはあろう垂直の岩壁の真下の薄闇がひどく気味悪かった。そのあたりには黒い海が入り込んでいて、白く泡だった海水が、何か得体の知れない獣が蠢(うごめ)き息づいているように見えたからだった。
降路の正面には崖下からそそり立つ二つの岩塔が黒々と立ちはだかっていたが、ちょうどそれは高さ四十メートルを越える大岩塊を、巨大な鉈で一気に割り裂いたもののように見えた。
「あれが地獄?」と聞くと、低い声で「違うよ、あれは地獄の門」とSは答える。
下りきった地獄の門のあたりは薄闇に包まれていた。湿った空気の漂いの中で、Sの顔が微笑んだ。
「あの門をくぐって、二人で地獄に落ちようよ」
私の背すじを、またしても冷たいものが走った。別に怯えていたわけでもないのに、「おどかさないでよ」と言う私の声は少し嗄(か)れていた。
地獄の門の岩壁の狭間には細い道が吸い込まれていたが、その限られた狭い空間の向こうには明るく白い海が光っていた。
そこは岩塊がごろごろと積み重なっている岩礁で、足元の岩盤の溝には赤茶けた水がたまっていた。磯の香に混じって、異様な臭いが鼻をかすかに刺激した。
「三途の川よ」と言って、Sは溝を飛び越えた。
大岩をぐるりと回ると、その岩陰にかなり大きなタイドプール(引き潮の時、海岸の岩間に海水が取り残されてできる水溜り)があった。しかしそれはただのタイドプールではなくて、水面に白い湯気を漂わせている海辺に湧く温泉だった。「そういえば、この島は火山島だったっけ」と、今さらのように私は温泉の存在を認識するのだった。
「なーんだ、温泉か!」
「そうさ、坊やを洗ってやろうと思ってね」
天然の岩風呂は三方を大岩に囲まれ、海側だけが開いていて、そこから岩の裂け目を通じてすぐ前の海と連絡していた。波が寄せるたびに海水は湯船の中に少しずつ入り込んでいた。大潮の時はたぶん海面下になるのだろう。付近の岩床や岩塊には薄緑の藻類が付着していた。湯船は広く、いくらか濁っていて底は見えなかった。奥は岩の陰で暗かった。前面の海には幾つもの岩礁が入江を鎧(よろ)うように立ち並び、それらはみな水蝕によって奇怪な形に削られていた。空にも海にもまだ残光があったが、背後を限る島の岩壁は上部のピンクを残してすでに夜の色だった。
私は平らな岩の上に腰を下ろして、傍らにランタンを置いてから言った。
「姉さんに、すっかりおどかされちゃった」
Sも私の横に腰を下ろし、笑って「地獄のことか……」
そして後を言わずに、じっと空を見上げていた。
「地獄か……」
再びSは独り言のように言ったまま、黙り込んでしまった。
2009年01月24日
地獄(3)
空に二つ、三つと星が現われはじめると、たちまちその数を増していった。私はランタンに灯を入れる。その炎はオレンジ色の柔らかな光の輪を周囲の岩に投げかけたが、その意外なほどの明るさも、湯船にはかすかに光を届かせるだけだった。
思い出したようにSが言った。
「入りなさいよ。汗を流すといいわ」
「でも熱くはない? 僕は猫なんだから」
「ぬるいから大丈夫だよ。さあ、タオルよ」と言う。
私がまだもじもじしているのを見ると、「恥ずかしいの? じゃあ、私は岩の後ろに退散するからさ」と言って立ち上がった。
私はその言葉に、「姉さんは入らないの?」と言いかけたが、思い直して口をつぐんだ。恥ずかしい気持ちが先に立ったのだ。
服を脱ぐと、海水の入り込むあたりから私はおそるおそる湯の中に足を滑り込ませた。湯はぬるく、底は粗い砂地だった。湯の中から、暗い磯に波が静かに砕けているのが見えた。空ももう夜で、数知れぬ星々が競うように輝き出していた。
「どお? お猫さん、いいお湯?」
岩の後ろからSの声がかかる。
「うん、とても! 星も素敵だし!」
しばらく間を置いて、またSの声がした。
「私も入ろうかな……いけない?」
「うん、いいさ」
もしかしたらと、そんな期待もないではなかった私だったが、いざとなると急に心臓の鼓動が高まった。
突然、はらりと岩越しに湯の中に白い物が投げ込まれた。続いて、ぱらりと投げ込まれた白い物は湯壷に浮いて強い匂いを湯の面に漂わせた。トベラの花だった。
岩間にちらりと白い肩らしいものを見てSが来るのを意識すると、私は目をそらせて湯船の奥に向き直った。
「向こう向いてて」と言うSの声。
身体を湿す湯の音に、閉じられた私の網膜は、すらりと長いSの足が湯の中に滑り込むのを捉えていた。
「匂うね、トベラの花……。もうこっち向いてもいいよ」
頭の上に束ねられた髪の毛を、双手を上げて直しながら言った。
「びっくりした? はしたない女だと思ったろう?」
「ううん、そんなこと……」
私はその先を何と言おうかと戸惑ったが、やっと「姉さんだもの、いいじゃない」と言った。
「そうだったね。白状するとね、島の若い男や女達はここへよく入りにくるのよ。混浴ね。島では当たり前のことなんだけど、東京に住んでいた私は島に友達もいなかったし、村の人と一緒に入る気になんかなれなかった。でも、ちょっぴり混浴のスリルも経験してみたい、なんて気はあったのさ。そこへ坊やというカモでしょ」
「でも、今ここへ村の人が来るカモよ」
「来っこないさ。そういう時と日を選んだんだもの。でも難しいのよ、このお湯の時間。満潮でも、潮が退きすぎていてもいけないし、雨でも駄目。昼間は人が来るし、それに今は海老の漁期で村の人は忙しいから来ないよ」
「それにしても、演出は満点だったよ。姉さんは芝居がうまいよ。すっかりかつがれちゃった」
「フフフフ」
岩の簀(すのこ)に腰を下ろした私の背中を、Sはごしごしと海綿でこすってくれた。
「案外、筋肉がついているね。山やスキーをやっているからかな。さあ、もういいよ」
平手でピシャリと背中を叩かれて、私は湯船に飛び込んだ。
Sは海に向かって両腕を上げ、髪を結っている。ランタンの淡い光を片側に受けて、白い背や腕が星をちりばめた空に浮く。やはり女らしいふくよかな線だった。
私はヨットの中でSから聞いた、人魚の話を思い出していた。N島のA神社にまつわる話である。
昔、ある鮑(あわび)採りの漁師が近くの磯で潜水していると、海底の岩の上に子どもを抱いた人魚が腰をかけているのを見つけた。人魚も人間にその姿を見られたことに気づくと、漁師に「お願いだから、私の姿を見たことをほかの人に言わないでください。でないと、私はあなたを取り殺さねばなりません」と頼んだ。漁師は十数年間その約束を守っていたが、ついにある会合の席で、酒の酔いも手伝ったのだろう、このことを自慢げに仲間達に話してしまった。その翌日の夜から漁師は急に高熱を出して、数日を経ずして死んでしまった。仲間はそれを知るとおののき恐れ、人魚を神にまつりA神社と名づけた。という物語である。
私はSの背に向かって声をかけた。
「姉さん、人魚みたいだ」
「馬鹿!」
Sは振り返ると、掌に湯を掬って私を目がけてひっかけた。そして私の逃げる隙にお湯の中に飛び込んだ。
「坊やがあんなこと言うものだから、腰から下に鱗が生えてきそうだよ」と言った。
「姉さん! 姉さん見たって言わないから、取り殺さないでよね」
「許せないよ、ゴルゴンにしてやる!」
沖に漁火らしい赤い灯が点々と連なっていた。ときたま海面が青白く光るのは、夜光虫だろうか? 灯台の投げかける光だろうか?
降るような星空だった。
トベラが匂う。暖められてにじみ出したその精油の匂いは強い。それはもはや香とはいえなかった。野生の匂い、妖しく悪魔的ともいえるその匂いは、私にはあまりにも刺激が強すぎた。花びらは白く点々と湯に浮かび、Sの丸い二の腕にまつわりついて離れようとはしなかった。
思い出したようにSが言った。
「入りなさいよ。汗を流すといいわ」
「でも熱くはない? 僕は猫なんだから」
「ぬるいから大丈夫だよ。さあ、タオルよ」と言う。
私がまだもじもじしているのを見ると、「恥ずかしいの? じゃあ、私は岩の後ろに退散するからさ」と言って立ち上がった。
私はその言葉に、「姉さんは入らないの?」と言いかけたが、思い直して口をつぐんだ。恥ずかしい気持ちが先に立ったのだ。
服を脱ぐと、海水の入り込むあたりから私はおそるおそる湯の中に足を滑り込ませた。湯はぬるく、底は粗い砂地だった。湯の中から、暗い磯に波が静かに砕けているのが見えた。空ももう夜で、数知れぬ星々が競うように輝き出していた。
「どお? お猫さん、いいお湯?」
岩の後ろからSの声がかかる。
「うん、とても! 星も素敵だし!」
しばらく間を置いて、またSの声がした。
「私も入ろうかな……いけない?」
「うん、いいさ」
もしかしたらと、そんな期待もないではなかった私だったが、いざとなると急に心臓の鼓動が高まった。
突然、はらりと岩越しに湯の中に白い物が投げ込まれた。続いて、ぱらりと投げ込まれた白い物は湯壷に浮いて強い匂いを湯の面に漂わせた。トベラの花だった。
岩間にちらりと白い肩らしいものを見てSが来るのを意識すると、私は目をそらせて湯船の奥に向き直った。
「向こう向いてて」と言うSの声。
身体を湿す湯の音に、閉じられた私の網膜は、すらりと長いSの足が湯の中に滑り込むのを捉えていた。
「匂うね、トベラの花……。もうこっち向いてもいいよ」
頭の上に束ねられた髪の毛を、双手を上げて直しながら言った。
「びっくりした? はしたない女だと思ったろう?」
「ううん、そんなこと……」
私はその先を何と言おうかと戸惑ったが、やっと「姉さんだもの、いいじゃない」と言った。
「そうだったね。白状するとね、島の若い男や女達はここへよく入りにくるのよ。混浴ね。島では当たり前のことなんだけど、東京に住んでいた私は島に友達もいなかったし、村の人と一緒に入る気になんかなれなかった。でも、ちょっぴり混浴のスリルも経験してみたい、なんて気はあったのさ。そこへ坊やというカモでしょ」
「でも、今ここへ村の人が来るカモよ」
「来っこないさ。そういう時と日を選んだんだもの。でも難しいのよ、このお湯の時間。満潮でも、潮が退きすぎていてもいけないし、雨でも駄目。昼間は人が来るし、それに今は海老の漁期で村の人は忙しいから来ないよ」
「それにしても、演出は満点だったよ。姉さんは芝居がうまいよ。すっかりかつがれちゃった」
「フフフフ」
岩の簀(すのこ)に腰を下ろした私の背中を、Sはごしごしと海綿でこすってくれた。
「案外、筋肉がついているね。山やスキーをやっているからかな。さあ、もういいよ」
平手でピシャリと背中を叩かれて、私は湯船に飛び込んだ。
Sは海に向かって両腕を上げ、髪を結っている。ランタンの淡い光を片側に受けて、白い背や腕が星をちりばめた空に浮く。やはり女らしいふくよかな線だった。
私はヨットの中でSから聞いた、人魚の話を思い出していた。N島のA神社にまつわる話である。
昔、ある鮑(あわび)採りの漁師が近くの磯で潜水していると、海底の岩の上に子どもを抱いた人魚が腰をかけているのを見つけた。人魚も人間にその姿を見られたことに気づくと、漁師に「お願いだから、私の姿を見たことをほかの人に言わないでください。でないと、私はあなたを取り殺さねばなりません」と頼んだ。漁師は十数年間その約束を守っていたが、ついにある会合の席で、酒の酔いも手伝ったのだろう、このことを自慢げに仲間達に話してしまった。その翌日の夜から漁師は急に高熱を出して、数日を経ずして死んでしまった。仲間はそれを知るとおののき恐れ、人魚を神にまつりA神社と名づけた。という物語である。
私はSの背に向かって声をかけた。
「姉さん、人魚みたいだ」
「馬鹿!」
Sは振り返ると、掌に湯を掬って私を目がけてひっかけた。そして私の逃げる隙にお湯の中に飛び込んだ。
「坊やがあんなこと言うものだから、腰から下に鱗が生えてきそうだよ」と言った。
「姉さん! 姉さん見たって言わないから、取り殺さないでよね」
「許せないよ、ゴルゴンにしてやる!」
沖に漁火らしい赤い灯が点々と連なっていた。ときたま海面が青白く光るのは、夜光虫だろうか? 灯台の投げかける光だろうか?
降るような星空だった。
トベラが匂う。暖められてにじみ出したその精油の匂いは強い。それはもはや香とはいえなかった。野生の匂い、妖しく悪魔的ともいえるその匂いは、私にはあまりにも刺激が強すぎた。花びらは白く点々と湯に浮かび、Sの丸い二の腕にまつわりついて離れようとはしなかった。
2009年01月25日
Sの入江
入江の奥の海蝕崖の岩根に、波が寄せ集めてつくったのだろう、小さな砂浜があった。そこは海蝕崖に取り囲まれて一方だけが海に面していたが、その海にも岩礁が立ち並んでいて船からも砂浜はほとんど見ることができないという。「Sの入江」、そこへは引き潮の時だけ崖下の海沿いを歩いていくことができた。背後の切り立った断崖は頭上に覆い被さって、登ることも降ることもほとんど不可能のようだった。
Sがここを見つけたのは、少女の頃だったという。Sは誰も来ないここでの、孤独の時間を愛した。
私達が行った時、その小さな砂浜には何がここまで運んできたのか、ひと群れのハマダイコンが根を下ろし、薄紅の花を咲かせていた。二人はその花の傍らに仰向けに寝て、足を伸ばした。
この季節には珍しく三、四日続いた晴天も、今日は朝から霧が深かった。それでも日光は霧のヴェールを通して砂を温め、ぽかぽかと暖かかった。霧は海から生まれて島に押し寄せ、薄れながらも断崖に沿って這い上がる。太陽は鈍く海面は鉛の色だったが、ときたま波がきらりと光るのは、霧の薄れたところでもあったのだろうか。
「姉さんは、ほんとうはすごくロマンチストなんだと思うな」
寝たまま私は言った。
「ロマンチストは君の方だろ。夢を食べてる……そうだろう。獏みたいな子」
「それで生きていけたらいいな。だけど僕には食べさせてやらなければならない母や弟妹がいるんだ。でも僕は生まれつきのんきにできてるから……」
それきりSは黙った。私は両手を頭の下に当てがい、目を閉じた。
私の頭の中に、忘れたはずの思い出がまざまざと蘇った。海と、崖と、砂浜と……。私の若い心に、今も癒えない大きな傷跡を残したその出来事から私はいつも逃げようとしていたのだったが……。長者ヶ崎の小さな入江もM子の面影も、Sの傍らにいて私は素直に受け入れることができた。
M子と私は小学校の同級生だった。卒業して八年後、久しぶりに開かれたクラス会で再会したM子は、別人のように美しくなっていた。小学校時代、無口でおとなしかった彼女とは、ほとんど口をきいたことがなかったように思う。クラス会の翌日、会の幹事だったM子と私は、上野の喫茶店で会って今後の会の運営等について話し合った。ベランダを取り囲む花壇の燃えるようなサルビアの花を、私はいまだに忘れることができない。その頃、私の父が事業に失敗して行方不明になっていた事情と、M子の父が破産を苦に自殺してしまった事件が二人を急速に接近させていった。
葉山にあったM子の家の別荘が人手に渡されることになった最後の夏、それは私の学生時代最後の夏休みでもあった。その頃、一色の海岸に私はよくM子と渚伝いに行って、時を過ごした。葉山御用邸の付近は、水着では歩けなかった時代のことである。話すことはあまりなかったと思う。ただ二人でいるだけでよかった。お互いの境遇には触れたくなかったのだ。小声で合唱することが多かった。M子は美しいアルトの持ち主だったのである。
その後、M子はあるデパートのネクタイ売り場に勤めるようになり、私は社会人として巣立った。お互いの境遇を知り合っているM子と私は、M子の結婚の時が二人の別離の時であることが、わかり過ぎるほどわかっていた。
M子との別れの日、私達は想い出の多い長者ヶ崎で落ち合った。晩秋の冷たい風の中で、初めて手を取り合ってお互いの幸せを誓い合ったが、涙が溢れた。しかし、別離の時刻(とき)は意外にあっさりと経過した。彼女の冷たく柔らかい指の感触と、二人で拾った桜貝の二片だけが私に残された。
苦しさは、むしろ後から追いかけてきた。時の経過とともに、気の狂いそうな苦しさが私を襲った。別れがこんなにも苦痛なものであるならば、私はもう絶対に恋はすまいと思ったものだ。
山好きの私が逃避の場を山に求めたのは当然の成り行きといえた。たった一人の長い山旅が始まった。霧の山稜に行き暮れたり、より困難な岩場を求めて彷徨したあの頃の単独行を思うと、遭難しなかったのがむしろ不思議に思われる。私は前途に何の希望も持てなかったのだ。ただ、家族のために生きねばならないという使命感が、私に幸いしたというべきかもしれない。
長いこと私は黙っていた。
時の経過の中で、私は小声でハミングしていた。シューベルトの「海辺にて」だった。いつの間にかそれにハミングで合わせていたSが、起き上がると言った。
「何を考えていたの? ぼけっとして」
私はそれには答えず、「姉さん、もう潮が満ちてくる頃じゃない? もう帰ろうよ」と言った。
「いいさ、満ちてくればいい」とSは言い、間を措(お)いて、「私は泳いで帰るから」と言う。
「意地悪。着てる物どうするのさ」
「丸めて頭にくっつけるよ」
「水着も持ってないのに……。僕は姉さんのこと心配してやってるんだ。いいよ、僕も泳いで帰るから……」
「この辺の海は暗礁が多いんだよ。糸くらげもワンサといて、体中が腫れあがるよ」
「いやだなあ。じゃあ、どうするのさ」
「心配しなくてもいいよ。この崖を登って帰るから……」と、後ろの断崖を振り返る。
「また冗談を言う」
私も断崖を見上げた。
「私の見つけたルートがあるのさ、心配するなよ。坊やだって岩登りくらいやるのだろう? 登れないんだったら、一人で先に帰りなよ」と、Sは素っ気ない。
私は立ち上がって改めて周囲の岩壁を見回したが、攀じ登れそうな所はどこも見当たらなかった。
「登れないよ、これは……。ザイルもハーケンもなしにはね」
「そんなもの要らないよ。でも少し手強いぞ。ほら、あの壁を斜めに横切っているバンド(岩壁に帯のように絡んだ階段状の所)に取り付けば、壁をトラバース(横切る)して向こうのリッジ(狭い岩稜)に出られる。後は半分木登りだよ」
「バンドの真中が切れてるじゃないか、あそこはどうする? 跳び移るなんて僕はいやだよ。だいたい跳び越せるほど狭くはないよ」
「そう、あそこが一番悪いんだ。でもここからは見えないけど、あのチムニー(縦に入った岩の裂け目)には大きなチョックストーン(岩の裂け目の中に挟まっている岩塊)が一個あるんだ。それに乗っかって渡ればいい。チョックストーンがなくなっていなければだけどね」
「ウェー、いやだな。下は海だぜ」
「下を見なけりゃいいさ。いやなら早く帰りな」と、Sは言うのである。
私は覚悟を決めた。女の登れる所である。私はまた砂の上にひっくり返った。
「ええ、登りゃあいいんでしょ。登りゃあ」
「そうそう。いい子だ、いい子だ。チョコレートやろうか」
Sの出したチョコレートを口に放り込んで、私はゆっくり舌の上で溶かした。
霧は音もなく海を渡ってくる。一面ミルク色の空間に、奇怪な岩礁の影が幻のように濃淡を浮かばせていた。ときどき鳴き声を残して、鴫(しぎ)が姿を現わしては消える。波はピチャピチャと砂と戯れているだけだった。
こんな時を持つことを期待して、私は何年も前から待ち続けていたような気がしていた。
「さっきの歌、歌おうか」
Sはシューベルトの「海辺にて」を、ハイネの原詩で歌いだした。私は黙ってその声が霧に溶けて、あたりにくぐもり響くのを聴いていた。
岩壁も、砂も、ハマダイコンの花も、霧の包むすべてのものは濡れて重かった。
Sがここを見つけたのは、少女の頃だったという。Sは誰も来ないここでの、孤独の時間を愛した。
私達が行った時、その小さな砂浜には何がここまで運んできたのか、ひと群れのハマダイコンが根を下ろし、薄紅の花を咲かせていた。二人はその花の傍らに仰向けに寝て、足を伸ばした。
この季節には珍しく三、四日続いた晴天も、今日は朝から霧が深かった。それでも日光は霧のヴェールを通して砂を温め、ぽかぽかと暖かかった。霧は海から生まれて島に押し寄せ、薄れながらも断崖に沿って這い上がる。太陽は鈍く海面は鉛の色だったが、ときたま波がきらりと光るのは、霧の薄れたところでもあったのだろうか。
「姉さんは、ほんとうはすごくロマンチストなんだと思うな」
寝たまま私は言った。
「ロマンチストは君の方だろ。夢を食べてる……そうだろう。獏みたいな子」
「それで生きていけたらいいな。だけど僕には食べさせてやらなければならない母や弟妹がいるんだ。でも僕は生まれつきのんきにできてるから……」
それきりSは黙った。私は両手を頭の下に当てがい、目を閉じた。
私の頭の中に、忘れたはずの思い出がまざまざと蘇った。海と、崖と、砂浜と……。私の若い心に、今も癒えない大きな傷跡を残したその出来事から私はいつも逃げようとしていたのだったが……。長者ヶ崎の小さな入江もM子の面影も、Sの傍らにいて私は素直に受け入れることができた。
M子と私は小学校の同級生だった。卒業して八年後、久しぶりに開かれたクラス会で再会したM子は、別人のように美しくなっていた。小学校時代、無口でおとなしかった彼女とは、ほとんど口をきいたことがなかったように思う。クラス会の翌日、会の幹事だったM子と私は、上野の喫茶店で会って今後の会の運営等について話し合った。ベランダを取り囲む花壇の燃えるようなサルビアの花を、私はいまだに忘れることができない。その頃、私の父が事業に失敗して行方不明になっていた事情と、M子の父が破産を苦に自殺してしまった事件が二人を急速に接近させていった。
葉山にあったM子の家の別荘が人手に渡されることになった最後の夏、それは私の学生時代最後の夏休みでもあった。その頃、一色の海岸に私はよくM子と渚伝いに行って、時を過ごした。葉山御用邸の付近は、水着では歩けなかった時代のことである。話すことはあまりなかったと思う。ただ二人でいるだけでよかった。お互いの境遇には触れたくなかったのだ。小声で合唱することが多かった。M子は美しいアルトの持ち主だったのである。
その後、M子はあるデパートのネクタイ売り場に勤めるようになり、私は社会人として巣立った。お互いの境遇を知り合っているM子と私は、M子の結婚の時が二人の別離の時であることが、わかり過ぎるほどわかっていた。
M子との別れの日、私達は想い出の多い長者ヶ崎で落ち合った。晩秋の冷たい風の中で、初めて手を取り合ってお互いの幸せを誓い合ったが、涙が溢れた。しかし、別離の時刻(とき)は意外にあっさりと経過した。彼女の冷たく柔らかい指の感触と、二人で拾った桜貝の二片だけが私に残された。
苦しさは、むしろ後から追いかけてきた。時の経過とともに、気の狂いそうな苦しさが私を襲った。別れがこんなにも苦痛なものであるならば、私はもう絶対に恋はすまいと思ったものだ。
山好きの私が逃避の場を山に求めたのは当然の成り行きといえた。たった一人の長い山旅が始まった。霧の山稜に行き暮れたり、より困難な岩場を求めて彷徨したあの頃の単独行を思うと、遭難しなかったのがむしろ不思議に思われる。私は前途に何の希望も持てなかったのだ。ただ、家族のために生きねばならないという使命感が、私に幸いしたというべきかもしれない。
長いこと私は黙っていた。
時の経過の中で、私は小声でハミングしていた。シューベルトの「海辺にて」だった。いつの間にかそれにハミングで合わせていたSが、起き上がると言った。
「何を考えていたの? ぼけっとして」
私はそれには答えず、「姉さん、もう潮が満ちてくる頃じゃない? もう帰ろうよ」と言った。
「いいさ、満ちてくればいい」とSは言い、間を措(お)いて、「私は泳いで帰るから」と言う。
「意地悪。着てる物どうするのさ」
「丸めて頭にくっつけるよ」
「水着も持ってないのに……。僕は姉さんのこと心配してやってるんだ。いいよ、僕も泳いで帰るから……」
「この辺の海は暗礁が多いんだよ。糸くらげもワンサといて、体中が腫れあがるよ」
「いやだなあ。じゃあ、どうするのさ」
「心配しなくてもいいよ。この崖を登って帰るから……」と、後ろの断崖を振り返る。
「また冗談を言う」
私も断崖を見上げた。
「私の見つけたルートがあるのさ、心配するなよ。坊やだって岩登りくらいやるのだろう? 登れないんだったら、一人で先に帰りなよ」と、Sは素っ気ない。
私は立ち上がって改めて周囲の岩壁を見回したが、攀じ登れそうな所はどこも見当たらなかった。
「登れないよ、これは……。ザイルもハーケンもなしにはね」
「そんなもの要らないよ。でも少し手強いぞ。ほら、あの壁を斜めに横切っているバンド(岩壁に帯のように絡んだ階段状の所)に取り付けば、壁をトラバース(横切る)して向こうのリッジ(狭い岩稜)に出られる。後は半分木登りだよ」
「バンドの真中が切れてるじゃないか、あそこはどうする? 跳び移るなんて僕はいやだよ。だいたい跳び越せるほど狭くはないよ」
「そう、あそこが一番悪いんだ。でもここからは見えないけど、あのチムニー(縦に入った岩の裂け目)には大きなチョックストーン(岩の裂け目の中に挟まっている岩塊)が一個あるんだ。それに乗っかって渡ればいい。チョックストーンがなくなっていなければだけどね」
「ウェー、いやだな。下は海だぜ」
「下を見なけりゃいいさ。いやなら早く帰りな」と、Sは言うのである。
私は覚悟を決めた。女の登れる所である。私はまた砂の上にひっくり返った。
「ええ、登りゃあいいんでしょ。登りゃあ」
「そうそう。いい子だ、いい子だ。チョコレートやろうか」
Sの出したチョコレートを口に放り込んで、私はゆっくり舌の上で溶かした。
霧は音もなく海を渡ってくる。一面ミルク色の空間に、奇怪な岩礁の影が幻のように濃淡を浮かばせていた。ときどき鳴き声を残して、鴫(しぎ)が姿を現わしては消える。波はピチャピチャと砂と戯れているだけだった。
こんな時を持つことを期待して、私は何年も前から待ち続けていたような気がしていた。
「さっきの歌、歌おうか」
Sはシューベルトの「海辺にて」を、ハイネの原詩で歌いだした。私は黙ってその声が霧に溶けて、あたりにくぐもり響くのを聴いていた。
岩壁も、砂も、ハマダイコンの花も、霧の包むすべてのものは濡れて重かった。
2009年01月26日
島を去る日
島を去る日、まだ陽の昇らない早朝、私は床から起き出した。四日間が瞬く間に過ぎて今日は五日目。いくら捨て猫の身分とはいえ、気がひけていた私である。「明後日には私も帰るから」というSに、「明日はちょうど船の便があるから」と帰京を宣言したのは昨日のことである。Sも止めなかった。
泊まり賃など取ってもらえないのはわかっていた。お礼代わりに、花壇に秋の花でも植えて帰ろうと思いついたのだ。苗床にはちょうど移植時期を迎えた百日草、マリーゴールド、サルビア、鶏頭等の苗が、緑の頭を寄せ合っていた。
私はそっと庭に下り立ち、物置から鍬を取り出して花壇を耕した。腐葉土を鋤きこんでから表土を整える。私は柄にもなく花を作ることが好きだったので、手際も悪くはなかった。苗を半分ほども移植し終わった頃、起き出してきたSの母上はそれを見ると目を輝かせた。
「植えてくれているのね。すまないわね。植えるのはともかく、女の私には耕すのが骨が折れて。ほんとうにありがとうね。このお花の咲く日が楽しみだわ。また秋になったら今度はお花を見に来てくださいね。是非ね」
私の思いを遥かに越えた喜びように、私はふと東京の母の面影を見た。
「そうだ、早く帰ろう。おふくろは心配しているだろう」
私は帰京の日を今日に決めたことを、ほんとうに良かったと思った。
別れの時間の長いのは嫌いだというSとは、玄関で別れた。しかし私達の間では、十日後に東京で再会する約束ができていた。八重洲口に近いH苑という喫茶店(それは、その後のSとの山行の打ち合わせにいつも使われた店だったが)に、五時半という時間まで決められていた。
Sの母上は、「ついでに用事を足すから、波止場までご一緒しましょう」と言って、私と一緒に家を出た。港への道々、彼女は自分が東京の山の手K町に生まれて育ったこと、ご主人を亡くした時、東京へ帰ろうと思ったが、すでに亡くなっていた両親のいない家には帰りづらく、島に留まってご主人の墓を守る生活に入ってしまったこと等を話してくれた。
「東京はなつかしいわ。それは、今の生活は平和だし、島の人も皆いい人達で親切にしてくれるのだけど、島では何といっても私は他国者(よそもの)。どうしても紙一枚馴染めないところがあって……東京に帰りたいわ。海を見ていると、ひとりでに涙が出てきてしまう時があるのよ。おかしいでしょ」
私は何と答えてよいのかわからなかった。あの大きな家に穏やかに住まう人にも悩みがあったのだと思うと、生きて求める人間の哀しさに胸がふさがれる思いだった。
わずかな貯金を生活の足し前にして、ただ子供達のたまさかの喜びにはともに笑い、その無軌道さには胸を痛めながら生きる以外、前途に期待する何物もなくなった私の母と、いずれが幸せなのだろうか。
艀に乗ろうとする私に、Sの母上はお土産の紙包みを渡しながら言った。
「お母さんによろしくね。長いこと引き留めてすみませんでしたと、謝っていたと言ってね」
その土産は、私が切符を買っている間に、彼女が港の市場で買い求めたものだった。
遠ざかる艀の中から、桟橋に立ちつくすSの母上の小さな姿がずっと見えていた。「さようなら、お幸せに」
私の目は潤んでいた。
客船に移るとすぐ、私は上甲板に上った。最高点でも百メートルに満たないS島は台地状の平らな島で、わけもなく海に沈んでしまいそうに私の目には映った。
「さようなら」
再び私は口には出さずに別れを告げた。
しかし出帆の汽笛が鳴ったその時、一艘の白いヨットが岬を回って近づいてくるのに気がついた。Sは彼女らしい方法で、見送りに来てくれたのだった。旅客船はスピードを上げる。ダフネの甲板で手を振っているSの姿が見えた。私も思いっきり手を振ってそれに応えた。ダフネと私との距離は次第に開いていった。波間に揺れ、浮かぶその姿は、一羽の白鳥に似ていた。私は誰もいない上甲板の手摺にもたれて、遠ざかるその白鳥を追っていた。
荒海を描くS、真昼の帆走、夕闇の湯浴み、霧の入江……。次々とその光景が脳裏をよぎる。
私の網膜に、白鳥はもう点となっていた。
*「トベラの島」の続編にあたる「青春挽歌」も、引き続きお読みいただけたらと思います。
泊まり賃など取ってもらえないのはわかっていた。お礼代わりに、花壇に秋の花でも植えて帰ろうと思いついたのだ。苗床にはちょうど移植時期を迎えた百日草、マリーゴールド、サルビア、鶏頭等の苗が、緑の頭を寄せ合っていた。
私はそっと庭に下り立ち、物置から鍬を取り出して花壇を耕した。腐葉土を鋤きこんでから表土を整える。私は柄にもなく花を作ることが好きだったので、手際も悪くはなかった。苗を半分ほども移植し終わった頃、起き出してきたSの母上はそれを見ると目を輝かせた。
「植えてくれているのね。すまないわね。植えるのはともかく、女の私には耕すのが骨が折れて。ほんとうにありがとうね。このお花の咲く日が楽しみだわ。また秋になったら今度はお花を見に来てくださいね。是非ね」
私の思いを遥かに越えた喜びように、私はふと東京の母の面影を見た。
「そうだ、早く帰ろう。おふくろは心配しているだろう」
私は帰京の日を今日に決めたことを、ほんとうに良かったと思った。
別れの時間の長いのは嫌いだというSとは、玄関で別れた。しかし私達の間では、十日後に東京で再会する約束ができていた。八重洲口に近いH苑という喫茶店(それは、その後のSとの山行の打ち合わせにいつも使われた店だったが)に、五時半という時間まで決められていた。
Sの母上は、「ついでに用事を足すから、波止場までご一緒しましょう」と言って、私と一緒に家を出た。港への道々、彼女は自分が東京の山の手K町に生まれて育ったこと、ご主人を亡くした時、東京へ帰ろうと思ったが、すでに亡くなっていた両親のいない家には帰りづらく、島に留まってご主人の墓を守る生活に入ってしまったこと等を話してくれた。
「東京はなつかしいわ。それは、今の生活は平和だし、島の人も皆いい人達で親切にしてくれるのだけど、島では何といっても私は他国者(よそもの)。どうしても紙一枚馴染めないところがあって……東京に帰りたいわ。海を見ていると、ひとりでに涙が出てきてしまう時があるのよ。おかしいでしょ」
私は何と答えてよいのかわからなかった。あの大きな家に穏やかに住まう人にも悩みがあったのだと思うと、生きて求める人間の哀しさに胸がふさがれる思いだった。
わずかな貯金を生活の足し前にして、ただ子供達のたまさかの喜びにはともに笑い、その無軌道さには胸を痛めながら生きる以外、前途に期待する何物もなくなった私の母と、いずれが幸せなのだろうか。
艀に乗ろうとする私に、Sの母上はお土産の紙包みを渡しながら言った。
「お母さんによろしくね。長いこと引き留めてすみませんでしたと、謝っていたと言ってね」
その土産は、私が切符を買っている間に、彼女が港の市場で買い求めたものだった。
遠ざかる艀の中から、桟橋に立ちつくすSの母上の小さな姿がずっと見えていた。「さようなら、お幸せに」
私の目は潤んでいた。
客船に移るとすぐ、私は上甲板に上った。最高点でも百メートルに満たないS島は台地状の平らな島で、わけもなく海に沈んでしまいそうに私の目には映った。
「さようなら」
再び私は口には出さずに別れを告げた。
しかし出帆の汽笛が鳴ったその時、一艘の白いヨットが岬を回って近づいてくるのに気がついた。Sは彼女らしい方法で、見送りに来てくれたのだった。旅客船はスピードを上げる。ダフネの甲板で手を振っているSの姿が見えた。私も思いっきり手を振ってそれに応えた。ダフネと私との距離は次第に開いていった。波間に揺れ、浮かぶその姿は、一羽の白鳥に似ていた。私は誰もいない上甲板の手摺にもたれて、遠ざかるその白鳥を追っていた。
荒海を描くS、真昼の帆走、夕闇の湯浴み、霧の入江……。次々とその光景が脳裏をよぎる。
私の網膜に、白鳥はもう点となっていた。
*「トベラの島」の続編にあたる「青春挽歌」も、引き続きお読みいただけたらと思います。
2009年01月27日
石老山顕鏡寺(1)
注:「トベラの島」がこの作品「青春挽歌」の前編になります。
Sとの別離は同時に、私の青春への離別となった。二十六才の晩秋の一日を、私は一生忘れることができないだろう。
幾度か訪れるうちにすっかり親しみ深い町となってしまった与瀬(よせ)だったが、今日のように静かで陰深い与瀬の町は初めてだった。日曜とはいえ、さすがに師走が近いのだ。都会のハイカーの姿も見当たらず、土地の人の影さえほとんど見えなかった。見覚えのある土蔵の傍らに、真紅の鶏頭の花が爛熟した頭を重そうに垂れている。夏は、確かそのあたりにおしろい花が咲き乱れていた。
与瀬という町の名は、山窩(さんか)のヨセバ(寄合場)からきたのだという。昔は、山窩の集合所だったのだろう。道にはうっすらと霜が降りている。
Sはさっきから、道に捨てられてあったさつま薯を蹴とばしながら歩いている。薯の半面は白い霜だったが、今は赤茶けた表皮に無数の傷ができて無惨な姿になっている。
町を通り抜け、道は次第に下っていって桂川を吊橋で渡る。橋の真中で薯はついに川の中に蹴落とされた。白茶けた拳大の塊が音もなく落ちていき、小さな波紋を残して水中に吸い込まれる。青黒に何ともいいようのない色の流れが渦巻き、淀み、後から後から止めどなく押し流されてゆく。
川上は、積み重なった段丘の間に屈曲して見えない。そして、もうそのあたりには冬の色しかない。十一月というのは、何と悲しい色を持っているのだろう。
Sとの山行も、今日限りでおしまいになるという。昨日そんな話を聞いて、急に思いたった山旅だった。過去三年の間、Sとの山行はたび重なって幾回になるだろう。北ア、秩父、上越、甲武相(こぶそう)、南アと、この山行の連続が、今日限りでおしまいになるというのは何といっても淋しいことだった。しかし、そのくせ何とはない安堵感のようなものが、私の胸の奥に生じたことも事実だった。なぜだか、私にはよくわかっていた。
三日前の電話でSは、「これが最後の山行よ」と言った。
川を越した道は、今度は段丘を上る。雑木林の中の道は急に細くなって、落葉が私達の足元でカサコソと鳴る。二人だけの足音がようやく山旅らしい感慨を誘う。幾曲がりかして登り切った小さな峠には、こましゃくれた石の地蔵さんがちょこなんと一人晩秋の光を浴びている。そしてその前に小さな黄色い草地があった。
「少し休んでいかない?」
私はザックを下ろして言う。Sは黙ってうなずく。
ほとんど葉の落ちた雑木の上に、甲武相国境の狐色の連嶺が長々と見渡される。それは澄み切った空の下に、暖かそうに陽を浴びた草の嶺である。
今年の春、小糠雨のそぼ降る日にあの向こう側の谷合を、同じSと歩いた日のことを思い出す。あの時、霧雨の中に手毬(てまり)のような紫陽花(あじさい)の花が幾つも幾つもぼーっと現われては消えた、妙に印象的な風景をふと思い浮かべる。
あの日、藍ねずのスーツを着ていたSは、今日は黒のワンピースを着ていた。すらりと背の高い混血のSには黒のワンピースがよく似合う。
引き締まった美しい姿態。私にはSがほんとうの姉のように思える時がある。三つばかり年上だからだろうが、今日の言葉少ないSは特にそうだ。そのことを言葉に出して言おうかなと思った時、急に下の方から下駄らしい足音が聞こえてきた。
やがて木の間に最初に現われたのは、小さな桃割れの頭だった。その晴着を着飾ったお百姓の娘さんは、私達に気がつくと恥ずかしそうにうつむいて小走りに前を通り抜けた。
後ろ姿を見送っていると、頭の桃割れがぴょこぴょこといつまでも桑畑の上に見えている。
「桃割れはいいなあ!」
Sが嘆息と一緒に言う。
「あの年頃がなつかしい? 姉さんもあんな時代があった?」と私が聞くと、「ところがないのよ。おかっぱで暴れているうちに、大人になっちゃった」と言って、彼女は立ち上がる。私もザックを背に立ち上がる。
2009年01月28日
石老山顕鏡寺(2)
道端には一寸ほどの霜柱が、真黒な土を被って並んでいる。ときおり頭の上で竹林がサヤサヤとさやぐ。この辺には竹林が多い。風が吹くたびに、ちかちかと葉末が光る。竹林は良い。直截で端正でいつもすがすがしい。
「石老山顕鏡寺」
石に刻まれた筆太の文字、いつか私達はその前に立っている。この禅寺が石老山の登り口だった。
私は禅寺が好きだ。何よりもそのひんやりと沈んだ空気の静かな漂いが好きだ。境内には大銀杏が二、三本、天に向かって大箒(ほうき)を逆さにしたように葉のない梢を聳立(しょうりつ)させていた。
「銀杏は征矢を射落として……」と歌った土井晩翠の詩さながらの姿で、青い天に向かって立っている。根元は一面に黄色い小扇を敷きつめている。Sは立ち上がって、その葉を二、三枚拾い上げる。
「奇麗だわ、この葉っぱ……」
子供のように目を輝かせて言う。
「僕はもっといいのを拾うぞ」
私もかがみ込んで拾う。二枚、三枚、五枚と、私の手に黄色い小扇が溜まる。Sも拾っている。
私はふと探すのを止めて、葉を拾うSの後ろ姿を見る。なぜかSの肩のあたりが思いのほかやつれて見える。その肩の向こうに冠木門(かぶきもん)が見える。
門内は顕鏡寺の掃き上げた庭である。冷たい風が、その辺りからそよそよと吹いてくる。ひっそりとして人の気配がない。
無から有へ、有から無へ、永劫(えいごう)に連なる無常感の古びた源泉がその辺りにある。東洋の哲学の静謐(せいひつ)が領している。
やつれて見えるSの肩。私はもう十年も前に、同じような肩を見た記憶がある。
十七か八の頃だった。初牛のお祭りの宵である。昼間の賑わいも去り、ローソクの灯の入った紙行灯だけが家の軒にゆらめいている黄昏時、私は四つ年上の叔母と散歩に出た。裏の稲荷には池があったが、その池のほとりに一本の木ささげがあった。稲荷も池も、私の曽祖父が屋敷内に造ったものだったが、その時この木も曽祖父が植えたものだったという。その木を背にして彼女は立ち止まった。いつになくしんみりとした口調で言う。
「キッちゃん、私もうじき遠いところへ行くの。キッちゃんはお母さんを大事にしてあげてね。たとえどんなことが起こっても、兄妹で力を合わせてね」
「どうして急にそんなこと言うの」
何やら急に不安な気持ちに襲われて、私は聞いた。
「何でもないの、ただなんとなく心配になったのよ……」
「道ちゃん、お嫁にいくんだろう……。おめでとうって言いたいけど、淋しいな、僕」
「道子だって淋しいわ。でもしょうがないでしょ……。キッちゃんがお坊ちゃんだから心配なの。さあ、もう行こう」
「なあんだ、馬鹿にしてらあ。お嫁さんの感傷か」
彼女はつと、木ささげの幹を離れて歩き出した。行灯の黄色い光が、彼女の肩から手先に流れる着物の線をすらりと浮き出させていた。それがなんとなくやつれて見えたのを、私は行灯の紙に描かれた初午の絵とともに鮮やかに思い出した。
それから二ヶ月後に叔母は大阪に嫁いでゆき、この五年の後、老舗であった私の家は潰れる。屋敷は人手に渡った。そんな経験があったせいか、Sは結婚するんだな……と私は直感した。昨日聞いた転勤なんてきっと嘘だと思う。その時、Sは私を振り向き、いぶかしげな顔をした。
「何をぼんやりしてるの、坊や」
彼女は背中に私の視線を感じたらしい。
「ううん、姉さんが今日はばかに女らしく見えるんで、みとれてたとこさ。
「ボンボンのくせに、生意気だぞ」とSはにらむ。
私達の手帳には、形のよい銀杏の二、三葉が選び出されて挟まれた。
「さあ行こう」
Sは先に立って歩き出す。私はまたしても過去の道子叔母との会話を思い出す。あの時と同じような会話。昔あったことの繰り返し。何だか、不吉な予感のようなものが私の背を走る……。
道は、ここからほんとうに山らしい登りとなる。
「石老山顕鏡寺」
石に刻まれた筆太の文字、いつか私達はその前に立っている。この禅寺が石老山の登り口だった。
私は禅寺が好きだ。何よりもそのひんやりと沈んだ空気の静かな漂いが好きだ。境内には大銀杏が二、三本、天に向かって大箒(ほうき)を逆さにしたように葉のない梢を聳立(しょうりつ)させていた。
「銀杏は征矢を射落として……」と歌った土井晩翠の詩さながらの姿で、青い天に向かって立っている。根元は一面に黄色い小扇を敷きつめている。Sは立ち上がって、その葉を二、三枚拾い上げる。
「奇麗だわ、この葉っぱ……」
子供のように目を輝かせて言う。
「僕はもっといいのを拾うぞ」
私もかがみ込んで拾う。二枚、三枚、五枚と、私の手に黄色い小扇が溜まる。Sも拾っている。
私はふと探すのを止めて、葉を拾うSの後ろ姿を見る。なぜかSの肩のあたりが思いのほかやつれて見える。その肩の向こうに冠木門(かぶきもん)が見える。
門内は顕鏡寺の掃き上げた庭である。冷たい風が、その辺りからそよそよと吹いてくる。ひっそりとして人の気配がない。
無から有へ、有から無へ、永劫(えいごう)に連なる無常感の古びた源泉がその辺りにある。東洋の哲学の静謐(せいひつ)が領している。
やつれて見えるSの肩。私はもう十年も前に、同じような肩を見た記憶がある。
十七か八の頃だった。初牛のお祭りの宵である。昼間の賑わいも去り、ローソクの灯の入った紙行灯だけが家の軒にゆらめいている黄昏時、私は四つ年上の叔母と散歩に出た。裏の稲荷には池があったが、その池のほとりに一本の木ささげがあった。稲荷も池も、私の曽祖父が屋敷内に造ったものだったが、その時この木も曽祖父が植えたものだったという。その木を背にして彼女は立ち止まった。いつになくしんみりとした口調で言う。
「キッちゃん、私もうじき遠いところへ行くの。キッちゃんはお母さんを大事にしてあげてね。たとえどんなことが起こっても、兄妹で力を合わせてね」
「どうして急にそんなこと言うの」
何やら急に不安な気持ちに襲われて、私は聞いた。
「何でもないの、ただなんとなく心配になったのよ……」
「道ちゃん、お嫁にいくんだろう……。おめでとうって言いたいけど、淋しいな、僕」
「道子だって淋しいわ。でもしょうがないでしょ……。キッちゃんがお坊ちゃんだから心配なの。さあ、もう行こう」
「なあんだ、馬鹿にしてらあ。お嫁さんの感傷か」
彼女はつと、木ささげの幹を離れて歩き出した。行灯の黄色い光が、彼女の肩から手先に流れる着物の線をすらりと浮き出させていた。それがなんとなくやつれて見えたのを、私は行灯の紙に描かれた初午の絵とともに鮮やかに思い出した。
それから二ヶ月後に叔母は大阪に嫁いでゆき、この五年の後、老舗であった私の家は潰れる。屋敷は人手に渡った。そんな経験があったせいか、Sは結婚するんだな……と私は直感した。昨日聞いた転勤なんてきっと嘘だと思う。その時、Sは私を振り向き、いぶかしげな顔をした。
「何をぼんやりしてるの、坊や」
彼女は背中に私の視線を感じたらしい。
「ううん、姉さんが今日はばかに女らしく見えるんで、みとれてたとこさ。
「ボンボンのくせに、生意気だぞ」とSはにらむ。
私達の手帳には、形のよい銀杏の二、三葉が選び出されて挟まれた。
「さあ行こう」
Sは先に立って歩き出す。私はまたしても過去の道子叔母との会話を思い出す。あの時と同じような会話。昔あったことの繰り返し。何だか、不吉な予感のようなものが私の背を走る……。
道は、ここからほんとうに山らしい登りとなる。
2009年01月30日
石老山頂(1)
湿った落葉に埋まった道は、足音も立たない。冷たく柔らかい感触だけが足裏に残る。そしてカサコソと二人の足の下で鳴る。私が冬近い山道を歩くのが好きなのは、この落葉の感触がなつかしいからだ。
風にはらはらと落葉が舞う。黄色い葉、赤茶色の葉、くるくる回りながらSの肩に舞いかかる。もう二日もすれば、すべての葉は落ち切ってしまうだろう。
去年の十月末、Sと歩いた上越国境、蓬峠の越路を思い出す。白樺の黄、ナナカマドの真紅、その落葉のふりかかる中を、上州から越後へと抜けた山旅……。あの時、一ノ倉の岩壁が周囲の紅葉(もみじ)で溶岩塊のように燃えていた。そして土樽(つちたる)へ下る私達の後ろから、追うように落ちてきたみぞれ。あんな旅ももうSとはできないのだと思うと、踏みしめるひとつひとつの枯葉にも感傷が残る。
山頂に近づくにしたがって、私達は汗ばんでくる。Sは袖をまくり上げ、私はチョッキを脱ぐ。頂上には露岩が多い。私達は大きな礫岩の陰に北風をよけ、日溜りの草の上に腰を下ろした。苦もなく着いてしまった山頂だった。
丹沢の幾重にも重なった山脈(やまなみ)を前にして、私達は午餐(ごさん)を摂った。テルモスの紅茶を飲むと、私はごろりと横になる。
「少し寝ようか?」
「うん」
こうして昼寝をすることは、もう山での慣わしになっている。いつもは簡単に眠り簡単に起きる私達だったが、今日はなかなか寝つかれなかった。私はまぶしさを防ぐために、Sのハンカチを取って顔に被せる。Sの常用の渋い匂いのする香水が、仄(ほの)かに鼻をくすぐる。それが次第に鼻について、よけい眠れなくなった。
ハンカチを取り去ると、Sの半身がコバルトの空に浮いている。Sは髪を梳かしている。櫛を持って、せわしく頭の上を往復している指に、裸の腕に、秋の陽がぴちぴちと跳ね返る。いつも日焼けして真黒な腕にもこんな美しい瞬間があるのかと思うと、何だかおかしくなって「ふふふ」と忍び笑いが出る。
「何がおかしいのよ」
「おかしいさ。姉さんがそんな女らしい格好をすることもあるのかと思うと、おかしくって……」
Sの柳眉が逆立つ。
「あるさ、女だもん」
丹沢山塊は紫色に沈んでいる。幾重にも重なった山脈(やまなみ)が、遠くなるにしたがって薄い青磁色に変わってゆく。右の方のさらに遠い山脈の上に、砂糖菓子のように白い頭を寄せ合っているのは初雪の南アルプスだろう。正面の中空には、忘れられた置物のような富士がぽかんと浮かんでいる。
突然、Sが言い出す。
「キッチン、私結婚することにしちゃった。十日後には『奥さん』って奴になるのよ……どう思う?」
予期していた言葉だったが、あらたまって言われると返事に困って、私はとぼけた」
「へぇー! 姉さんでも結婚できるの?」
私の言葉にSはぷんとして上を向く。その線の強いプロフィルの鼻の下に、例の置物の富士がぶら下がっている。
「まあいいさ。私だって女だもん、一度くらい結婚なんてものもしてみなくちゃ親不孝になるもの……。キッチン、君だって雄のハシクレなんだから、そのうちに結婚するんだろ……。それとも天の夕顔が一生忘れられないの? えへへ、知ってるぞM子のこと……」
私は驚いた。なぜSがM子のことを知っているのだろう。不思議だった。Sは私の眼を遠慮なくじろじろ覗き込む。いたずらっぽい眼の色だったが、その眼で見ていられたら私は頬のあたりが次第に火照り出し、加速度的に火照りが加わってついに真赤になってしまった。
「ウワーイ! 赤くなった、赤くなった」
Sは手を叩いて喜ぶ。そうされるとますます赤くなり、焦れば焦るほどいつまでたっても消えなくなった。
「いいとこあるね、やっぱりボンボンだね」
風にはらはらと落葉が舞う。黄色い葉、赤茶色の葉、くるくる回りながらSの肩に舞いかかる。もう二日もすれば、すべての葉は落ち切ってしまうだろう。
去年の十月末、Sと歩いた上越国境、蓬峠の越路を思い出す。白樺の黄、ナナカマドの真紅、その落葉のふりかかる中を、上州から越後へと抜けた山旅……。あの時、一ノ倉の岩壁が周囲の紅葉(もみじ)で溶岩塊のように燃えていた。そして土樽(つちたる)へ下る私達の後ろから、追うように落ちてきたみぞれ。あんな旅ももうSとはできないのだと思うと、踏みしめるひとつひとつの枯葉にも感傷が残る。
山頂に近づくにしたがって、私達は汗ばんでくる。Sは袖をまくり上げ、私はチョッキを脱ぐ。頂上には露岩が多い。私達は大きな礫岩の陰に北風をよけ、日溜りの草の上に腰を下ろした。苦もなく着いてしまった山頂だった。
丹沢の幾重にも重なった山脈(やまなみ)を前にして、私達は午餐(ごさん)を摂った。テルモスの紅茶を飲むと、私はごろりと横になる。
「少し寝ようか?」
「うん」
こうして昼寝をすることは、もう山での慣わしになっている。いつもは簡単に眠り簡単に起きる私達だったが、今日はなかなか寝つかれなかった。私はまぶしさを防ぐために、Sのハンカチを取って顔に被せる。Sの常用の渋い匂いのする香水が、仄(ほの)かに鼻をくすぐる。それが次第に鼻について、よけい眠れなくなった。
ハンカチを取り去ると、Sの半身がコバルトの空に浮いている。Sは髪を梳かしている。櫛を持って、せわしく頭の上を往復している指に、裸の腕に、秋の陽がぴちぴちと跳ね返る。いつも日焼けして真黒な腕にもこんな美しい瞬間があるのかと思うと、何だかおかしくなって「ふふふ」と忍び笑いが出る。
「何がおかしいのよ」
「おかしいさ。姉さんがそんな女らしい格好をすることもあるのかと思うと、おかしくって……」
Sの柳眉が逆立つ。
「あるさ、女だもん」
丹沢山塊は紫色に沈んでいる。幾重にも重なった山脈(やまなみ)が、遠くなるにしたがって薄い青磁色に変わってゆく。右の方のさらに遠い山脈の上に、砂糖菓子のように白い頭を寄せ合っているのは初雪の南アルプスだろう。正面の中空には、忘れられた置物のような富士がぽかんと浮かんでいる。
突然、Sが言い出す。
「キッチン、私結婚することにしちゃった。十日後には『奥さん』って奴になるのよ……どう思う?」
予期していた言葉だったが、あらたまって言われると返事に困って、私はとぼけた」
「へぇー! 姉さんでも結婚できるの?」
私の言葉にSはぷんとして上を向く。その線の強いプロフィルの鼻の下に、例の置物の富士がぶら下がっている。
「まあいいさ。私だって女だもん、一度くらい結婚なんてものもしてみなくちゃ親不孝になるもの……。キッチン、君だって雄のハシクレなんだから、そのうちに結婚するんだろ……。それとも天の夕顔が一生忘れられないの? えへへ、知ってるぞM子のこと……」
私は驚いた。なぜSがM子のことを知っているのだろう。不思議だった。Sは私の眼を遠慮なくじろじろ覗き込む。いたずらっぽい眼の色だったが、その眼で見ていられたら私は頬のあたりが次第に火照り出し、加速度的に火照りが加わってついに真赤になってしまった。
「ウワーイ! 赤くなった、赤くなった」
Sは手を叩いて喜ぶ。そうされるとますます赤くなり、焦れば焦るほどいつまでたっても消えなくなった。
「いいとこあるね、やっぱりボンボンだね」
2009年01月31日
石老山頂(2)
M子の名前は、私には禁物だった。Sはうまい代名詞を使った。そういえば、私にとってM子は「天の夕顔」に違いなかった。私の青春は彼女によって花開き、彼女によって終わってしまったといえる。
M子を幸福にできる自信のなかった私は、自分から彼女を離れた。M子にしてもそうだったかもしれぬ。離れ難い二つの心は、私達自身の意志によって無惨にも引き離された。私の母もM子の母も、二人の将来を許していてくれたのに……。否、周囲の人が許していてくれたからこそよけい、その人々を犠牲にして私達が結ばれることはできないと判断したのだ。お互い長男と長女で、父をなくした私達の肩には、家族を養ってゆかねばならない責任が重くのしかかっていた。その上、M子には彼女の家の経済状況にとってまったく好都合な結婚の申し込みがあった。相手の男性は真面目な青年だった。理性と情熱の間に立って、ついに理性の道を選んだ私達だったが、別れて後の苦しみは経験のある人だけがわかってくれると思っている。
私は苦しみを忘れるために、暇さえあれば山を歩いた。生きていく希望をほとんど失って、死を予定しての危険な単独登山が幾度か行なわれた。しかし死と生との間にはいつも母や兄妹たちの幻影がちらついて、私に生への努力を続けさせた。手当たり次第に本を読んでM子を忘れようともした。気分を転換することもできず、いかにして生きるかの解答が得られぬままに、気の狂いそうな日々が続いた。
そうした傷心の旅の一日、伊豆大島南海岸で絵を描いていた男のような女の子Sと知り合った。Sは私より年上だったが妙に気が合い、急速に交際の度が深まった。危険な山行からSと二人の比較的平穏な山行に移り現在に至った経過を振り返れば、私の胸の痛手を徐々に癒し忘れさせてくれたのは実にSだったのだ。言いかえれば命の恩人、再生の恩人はSなのである。
Sと私、私達の山仲間に言わせれば「興味津々たる取り合わせ?」なのだそうだ。五尺四寸の引き締まった姿態のSは、男子服を着せれば男として通用しそうなほどたくましかった。それが男のような口をきき、男のように振舞うのだから、初対面の人は度肝を抜かれる。「僕」なんてのは良い方で、「ワシ」だとか、ときどきは「オレ」等と言った。なれそめのはじめからすっかり牛耳られた私はSを「姉さん」と呼び、彼女は私のことを「坊や」とか「ボンボン」とか呼んだ。良く言っても「キッチン」だった。
山仲間のある人は、私のことをSの「若い燕」だと言った。「やっぱり一種の恋人同士なんだろうな」と言う人もいた。「浮気者のコンビ」だとか、ひどい奴になると「セミ同性愛」等と言った。いろいろのことが言われるらしいが、さて「結婚する気なんだろうか」ということになると、誰も確かな答えが出なかったらしい。山仲間が想像をたくましくするのも当然だった。なぜなら私自身、Sが友だちなのか恋人なのかわからなかったのだから……。
恋愛を結婚へ続く道だと考えるなら、私達の友情は恋愛ではなかったとはっきり言える。結婚ということは二人とも考えていなかった。否、考えることを避けていた。しかし彼女のさっぱりとした態度、魅力ある教養には私は強く魅かれていた。ことに彼女の内面を知る人が少ないだけに、それを知っている私には魅力的だった。外面の強さに似ぬSの弱さ、それがどこからくるのか知らなかったが、なにか哀愁のようなものが彼女全体を包んでいる。
彼女とは誰よりも心置きなく話せた。だから彼女との山行は楽しく、Sがいないと私の心は気の抜けたビールのようにわびしかった。気の合った山友達を持った人は誰でも知っているあの気持ちよさ、信頼感、気の置けない雰囲気、そんなものがいつもSと私の間には存在しているのだった。
山旅に出た私達は、楽しく朗らかでいつも悪口を言い合っていたが、心の裏には言いしれぬ淋しさが満ちている。心に苦悩を持つ人が、思い出してふっと淋しさに襲われるあの淋しさが、二人の胸の去来するせいか。それだけではなかった。二人の心の間にはいいようのない空間、空虚が存在していた。それはたぶん、内省とか反省とかいわれる性質のものだったのだろう。終局において結婚のない男女の交際で、友情の支えになるものといっては、こうしたものだけがあるに違いないのだ。わたしたちの交際が絹を隔てた肌ざわりをいつまでも持ち続けることができたのは、この内省のもたらす空間の仕業だったのかもしれない。
「姉さんがお嫁にいくと、相棒がいなくなって淋しいな。だけどしょうがねえや……。姉さんが女だったってことが立派に証明されるんだから、おめでとうを言うよ」
「ボクが女だってことよくわかったろう。以後、女としてつき合いたまえ。何事もレディーファースト」と彼女は威張る。
「女に思われたいんなら、少し口のきき方も、らしくしなよ……。姉さん、お祝い何がいいんだい?」
「要りませんわ、山の思い出だけで沢山ですわっ……てな調子でいいんだろ、いやいいんでしょう」
急に女らしくシナをつくってSが言う。
「無理をしてるね。そんな調子じゃ結婚してもすぐ追い出されちゃうよ」
「追い出される? 逆に追い出すさ。いや追ん出るよ」
Sは意気軒昂(いきけんこう)と言う。
「どこの誰だか知らないが、旦那になる人にそぞろ同情を禁じ得ないね」
「ボクと結婚するっていうんだから、相応の覚悟はしてるんだろう。二、三日前に会ってみて、これなら一応イケると思った。尻に敷けそうな面(つら)してるわ」
「自身満々だね。だけど心配だよ、僕は……」
「心配なんてご無用。もともと結婚なんて面倒臭いことをする気はなかったんだから、いやになったら離婚しちゃうわ。そうなりゃ今度こそ思う存分山が歩けると思うと、むしろ嬉しいね」
私は長息慨嘆(ちょうそくがいたん)した。
「コーヒーでも沸かそうか」
Sはコッフェルに薬缶をかける。モカの香りが私の鼻をつく。
彼女はいつの山行も、コーヒーとスケッチブックを忘れない。おかげで私達の山上の饗宴(きょうえん)は、いつもコーヒーとチーズだった。チーズを噛みしめながらSのデッサンを見ている時の私の心は、世界の海図を眺める英国人(アングロサクソン)のように豊かになるのが常だった。この瞬間には貧乏なわが身の生活も忘れて、映画や小説の一場面の人間になれる。こんな時間が、私にときたまあってもよいはずなのだ。だが……。
「S……、僕はいつまでもこんなことしてていいんだろうか」
ふと淋しくなって、私は言う。
「姉さん、僕はどうしたらいいんだろう。姉さんに取り残されたからじゃないんだ。僕という人間の存在価値なんだ。あるのか、ないのか、僕にはわからない……」
私は言いかけてふと止める。
「よそう、こんな話し。一人で解決をつけるよ」
M子を幸福にできる自信のなかった私は、自分から彼女を離れた。M子にしてもそうだったかもしれぬ。離れ難い二つの心は、私達自身の意志によって無惨にも引き離された。私の母もM子の母も、二人の将来を許していてくれたのに……。否、周囲の人が許していてくれたからこそよけい、その人々を犠牲にして私達が結ばれることはできないと判断したのだ。お互い長男と長女で、父をなくした私達の肩には、家族を養ってゆかねばならない責任が重くのしかかっていた。その上、M子には彼女の家の経済状況にとってまったく好都合な結婚の申し込みがあった。相手の男性は真面目な青年だった。理性と情熱の間に立って、ついに理性の道を選んだ私達だったが、別れて後の苦しみは経験のある人だけがわかってくれると思っている。
私は苦しみを忘れるために、暇さえあれば山を歩いた。生きていく希望をほとんど失って、死を予定しての危険な単独登山が幾度か行なわれた。しかし死と生との間にはいつも母や兄妹たちの幻影がちらついて、私に生への努力を続けさせた。手当たり次第に本を読んでM子を忘れようともした。気分を転換することもできず、いかにして生きるかの解答が得られぬままに、気の狂いそうな日々が続いた。
そうした傷心の旅の一日、伊豆大島南海岸で絵を描いていた男のような女の子Sと知り合った。Sは私より年上だったが妙に気が合い、急速に交際の度が深まった。危険な山行からSと二人の比較的平穏な山行に移り現在に至った経過を振り返れば、私の胸の痛手を徐々に癒し忘れさせてくれたのは実にSだったのだ。言いかえれば命の恩人、再生の恩人はSなのである。
Sと私、私達の山仲間に言わせれば「興味津々たる取り合わせ?」なのだそうだ。五尺四寸の引き締まった姿態のSは、男子服を着せれば男として通用しそうなほどたくましかった。それが男のような口をきき、男のように振舞うのだから、初対面の人は度肝を抜かれる。「僕」なんてのは良い方で、「ワシ」だとか、ときどきは「オレ」等と言った。なれそめのはじめからすっかり牛耳られた私はSを「姉さん」と呼び、彼女は私のことを「坊や」とか「ボンボン」とか呼んだ。良く言っても「キッチン」だった。
山仲間のある人は、私のことをSの「若い燕」だと言った。「やっぱり一種の恋人同士なんだろうな」と言う人もいた。「浮気者のコンビ」だとか、ひどい奴になると「セミ同性愛」等と言った。いろいろのことが言われるらしいが、さて「結婚する気なんだろうか」ということになると、誰も確かな答えが出なかったらしい。山仲間が想像をたくましくするのも当然だった。なぜなら私自身、Sが友だちなのか恋人なのかわからなかったのだから……。
恋愛を結婚へ続く道だと考えるなら、私達の友情は恋愛ではなかったとはっきり言える。結婚ということは二人とも考えていなかった。否、考えることを避けていた。しかし彼女のさっぱりとした態度、魅力ある教養には私は強く魅かれていた。ことに彼女の内面を知る人が少ないだけに、それを知っている私には魅力的だった。外面の強さに似ぬSの弱さ、それがどこからくるのか知らなかったが、なにか哀愁のようなものが彼女全体を包んでいる。
彼女とは誰よりも心置きなく話せた。だから彼女との山行は楽しく、Sがいないと私の心は気の抜けたビールのようにわびしかった。気の合った山友達を持った人は誰でも知っているあの気持ちよさ、信頼感、気の置けない雰囲気、そんなものがいつもSと私の間には存在しているのだった。
山旅に出た私達は、楽しく朗らかでいつも悪口を言い合っていたが、心の裏には言いしれぬ淋しさが満ちている。心に苦悩を持つ人が、思い出してふっと淋しさに襲われるあの淋しさが、二人の胸の去来するせいか。それだけではなかった。二人の心の間にはいいようのない空間、空虚が存在していた。それはたぶん、内省とか反省とかいわれる性質のものだったのだろう。終局において結婚のない男女の交際で、友情の支えになるものといっては、こうしたものだけがあるに違いないのだ。わたしたちの交際が絹を隔てた肌ざわりをいつまでも持ち続けることができたのは、この内省のもたらす空間の仕業だったのかもしれない。
「姉さんがお嫁にいくと、相棒がいなくなって淋しいな。だけどしょうがねえや……。姉さんが女だったってことが立派に証明されるんだから、おめでとうを言うよ」
「ボクが女だってことよくわかったろう。以後、女としてつき合いたまえ。何事もレディーファースト」と彼女は威張る。
「女に思われたいんなら、少し口のきき方も、らしくしなよ……。姉さん、お祝い何がいいんだい?」
「要りませんわ、山の思い出だけで沢山ですわっ……てな調子でいいんだろ、いやいいんでしょう」
急に女らしくシナをつくってSが言う。
「無理をしてるね。そんな調子じゃ結婚してもすぐ追い出されちゃうよ」
「追い出される? 逆に追い出すさ。いや追ん出るよ」
Sは意気軒昂(いきけんこう)と言う。
「どこの誰だか知らないが、旦那になる人にそぞろ同情を禁じ得ないね」
「ボクと結婚するっていうんだから、相応の覚悟はしてるんだろう。二、三日前に会ってみて、これなら一応イケると思った。尻に敷けそうな面(つら)してるわ」
「自身満々だね。だけど心配だよ、僕は……」
「心配なんてご無用。もともと結婚なんて面倒臭いことをする気はなかったんだから、いやになったら離婚しちゃうわ。そうなりゃ今度こそ思う存分山が歩けると思うと、むしろ嬉しいね」
私は長息慨嘆(ちょうそくがいたん)した。
「コーヒーでも沸かそうか」
Sはコッフェルに薬缶をかける。モカの香りが私の鼻をつく。
彼女はいつの山行も、コーヒーとスケッチブックを忘れない。おかげで私達の山上の饗宴(きょうえん)は、いつもコーヒーとチーズだった。チーズを噛みしめながらSのデッサンを見ている時の私の心は、世界の海図を眺める英国人(アングロサクソン)のように豊かになるのが常だった。この瞬間には貧乏なわが身の生活も忘れて、映画や小説の一場面の人間になれる。こんな時間が、私にときたまあってもよいはずなのだ。だが……。
「S……、僕はいつまでもこんなことしてていいんだろうか」
ふと淋しくなって、私は言う。
「姉さん、僕はどうしたらいいんだろう。姉さんに取り残されたからじゃないんだ。僕という人間の存在価値なんだ。あるのか、ないのか、僕にはわからない……」
私は言いかけてふと止める。
「よそう、こんな話し。一人で解決をつけるよ」